
SNSで、牛乳給食を断る投稿に対して、
「集団生活なのに」
「子どもの成長に良くない」
「マルチだろ」
「モンペ」
というアンチコメントが来ているのを見ました。
「個性が大事」と言いながら、同じであることを強要する...
こんなダブルスタンダードこそ、教育にとって良くないことだと思います。
こんにちは!髙杉多希です。
訪問してくれてありがとうございます。
雑穀と野菜で作る家庭料理教室 たきさんちを主宰したり、
畑で雑穀や野菜を育てたりして、
Instagramで情報発信をしたりしています。
「たきちゃん」「たきさん」と名前で呼んでください♪
最近、SNSで「牛乳給食を断った」という投稿に対して、
さまざまなコメントが寄せられているのを見かけました。

「集団生活なのにわがままだ」
「子どもの成長に良くない」
「マルチ商法に洗脳されてるんじゃ?」
「モンスターペアレントだ」
……こんな風に、一方的に決めつけたり、
感情的に断罪するようなコメントも多く見受けられ、
正直、胸が苦しくなりました。
牛乳について調べれば調べるほど、
「これを知らないって大丈夫!?」
と思う情報も多く、
牛乳給食をやめる決断をしたお母さんも、
かなり悩んだだろうなと思うからです。
実は、わが家でも、子どもたちが小学生の頃に、
給食の牛乳を飲まない選択をしたことがあります。
アレルギーがあるわけではなく、
体質や食の価値観から判断してのことでした。
しかし、学校側からは「診断書が必要」と言われ、
医師に相談しても「病気ではないから診断書は書けない」と断られ……
結果的には、
教員の中にも「健康上の理由」から牛乳を飲まない人がいることがきっかけで、
曖昧ながらも“飲まない”という選択を認めてもらうことができました。
(だったら何で病院に行かされたの...)(診察料は取られました...)
でも、こうした選択が「特別扱い」と見なされたり、
否定的に受け取られること自体に、私は違和感を持ちます。
食の選択は、その人の健康だけでなく、
価値観や生き方にもつながる大切な行為です。
どうしてそれが尊重できないのでしょう?
「断るのは教員の手間になるから、牛乳は飲みたい子にあげればいい」
という意見もありましたが、
それでは、特定の子が金銭的にも得をした状態になりますし、
(牛乳の自己負担は年間約1万円)(補助金が出るのであれば尚更)
子どもに牛乳2本は飲み過ぎにもなります。
実際に、教員がお持ち帰りして問題視され、
ニュースになったこともあると記憶しています。
子どもがその場で2本飲むのは良くて、教員が持って帰ることは悪?
その線引きは何でしょう?
また、注文してあると、気を利かせた先生が、
「一口飲んでみない?」「本当は飲みたいんじゃないの?」など、
親の目がない教室では、飲むことを強要してくることも。
断れば良い、と言われるかもですが、
先生は教室での絶対強者&年齢差で、
子どもにとっては飲んでも地獄、断るのも無理&苦痛。
その手間をかけるくらいなら、年度の初めに1筆書いた方が、
お互いに楽だと思いませんか?
実質問題として、牛乳を飲まない子どももいて、
飲みたくないけど、そう言うと面倒だから、
口をつけたふりや、一口飲んで捨てる...という子も。
これって、「やめる選択をする」ことよりもヒドいと思いませんか?
誰が得をするのでしょうか?
牛さんも牛乳の出し損です。
そもそも牛乳は健康にとって良いのか?
「牛乳は成長に必要不可欠」と言われ、
飲まないことによる影響を心配する人もいます。
しかし、現実には乳脂肪分による肥満や生活習慣病の増加も問題視されています。
カルシウムの主な摂取源とされていますが、
骨の丈夫さに牛乳の摂取量は関連性がなく、
むしろ牛乳の摂取量が多い国の方が、骨折率は高いというデータもあります。
身長の伸びと牛乳摂取の因果関係も科学的には明確ではありません。
そもそも日本では戦前まで牛乳を飲む習慣がありませんでした。
世界でも骨が丈夫な民族、と言われています。
近年の日本の病気の原因の多くが、
食の欧米化とされ、
なかでも消費量の上昇の激しいのが牛乳です。
噛まずに栄養摂取できる食べものは、
歯が生えた大人にとっては相応しくありません。
さまざまな資料が、牛乳と病気の関係を示してもいます。
では、なぜ変わらないのでしょうか?
そこには、畜産業と行政との密接な関係、
そして学校給食に対する国の補助制度が関係しています。
酪農家と経済を守るために?
たとえば、学校給食用牛乳には、国の補助金がついています。
これは、農業(特に酪農)支援の一環であり、
農林水産省と文部科学省の施策が重なって存在しているのです。
「子どもの健康のため」という名目が前面に出されますが、
実際には産業保護の側面が大きいという指摘もあります。
もちろん、地元の酪農家を支援するという意味では、
一定の意義はあるでしょう。
しかし、それが「全員に強制される」ことで、
本来守るべき「子どもたちの選ぶ自由」や、
「体質に合わせた柔軟な対応」が、
損なわれてしまっているのではないでしょうか。
実際、わが家では、長男が牛乳給食をやめた結果、
長年悩んでいた鼻炎が解消され、頭がスッキリした、と言っています。
長男も次男も、身長は180cm近くに伸び、腹筋も割れています(笑)。
もちろん、牛乳以外の食生活も大切です。
私も、未来食を学ぶ前は、
動物性のものがないことで不足した栄養をどう補うか?と考えたこともありましたが、
未来食を学び実践することで解決することを知り、実際に成長期を乗り切り、
もうその不安はありません。
自由にしたら子どものためにならない?
「でも自由にしたら、嫌いだから飲まない子が増える」
という声も聞かれます。
しかし、多くの大人に聞いたのは、
「牛乳を飲んでお腹を壊し続けていたがやめられなかった」
「牛乳を飲むまで帰れなくて泣いて飲んだ」
など、強要されることで人格を否定された記憶や、健康被害です。
例え嫌いだから飲まないという選択であっても、良いのではないでしょうか?
実際問題として、牛乳以外の食材でも、
子どもたちは食べたくないものは無理に食べないのが現代の学校です。
それなのに、牛乳だけ強要するって、
本当に子どものためになっているのでしょうか?
「でも貧困世帯では、子どもの貴重な栄養源になる」
と言った、子育て世帯の貧困問題を絡めて話す人もいます。
「選択的にやめられるようになったら、牛乳代をケチるためにやめる親がいる」
「給食無償化になったら、そういう親が牛乳を飲ませるようになった」
なんて声も聞かれます。
貧困問題と、牛乳の選択制は、まったく別の課題です。
それこそ、給食無償化を全国で行うことで、解決するのではないでしょうか?
また、「子どもの健康のために牛乳を飲まない選択をしたい」という方は、
「牛乳代金の返金にはこだわらない」という方がほとんどです。
もし、牛乳代をケチるために子どもの健康を損なう恐れを気にするなら、
牛乳を注文しなくても返金しないことにすれば、そのリスクも避けられます。
酪農は日本に向かない
さらに、酪農自体も多くの問題をはらんでいます。
エサを海外から輸入したり、酪農の運営自体が、
日本のみで完結できない仕組みとなっています。
また、人間が牛乳を飲むために、牛の一生を犠牲にしています。
しかも、先ほど話題にしましたが、牛乳を捨てている子どもも多く居ます。
母乳育児をしたことがある方なら分かるかと思いますが、
母体の血からできる、まさに母の身を削って生まれるモノが母乳です。
「だったら、その大変さを子どもに伝えればいい」とか、そういう問題じゃないんです。
「牛乳は飲みたくない」という自分の体の感覚を信じる力を身に着けてほしい。
食の自由を、主張でき、選択できるようにしてほしい。
そして...牛にも、母子ともに穏やかな時間を過ごしてほしいのです。
本当の多様性と集団生活で大切なこととは
「個性が大事」と言いながら、
実際には“みんなと同じであること”が重視される――
これは、教育現場だけでなく、
日本社会全体に共通する構造かもしれません。
私は、自分の子どもたちに、
「自分の体の声を聴いて、自分で選んでいいんだよ」と伝えたい。
そして、それを誰かが否定するような世の中ではなく、
お互いの選択を尊重し合える社会であってほしいと願っています。
もちろん、集団生活なので、
なんでもワガママを通す必要はありませんが、
食の選択は、その人の健康だけでなく、
価値観や生き方にもつながる大切な行為です。
だからこそ、
ひとりひとりが「何をどう食べるか」を自由に考えられる余白が、
社会にも学校にも、もっと必要だと思うのです。
「〇〇を増やしてほしい」ではないのです。
ただ「うちの子だけ牛乳をやめてほしい」のです。
注文数を1つ減らすだけなのです。
お金もかかりません。
どうしてそれができないのでしょうか?
「あなたはそう思うのね」
「私はこう思うわ」
「みんな同じ」で安心するのではなく、
「みんな違って、それでいい」からこそ、お互いの存在が豊かになる。
それが、本当の意味で“集団生活を学ぶ”ことではないでしょうか?
ひとつの出来事が浮き彫りにする背景は、複雑です。
でも、だからこそ、
これからも、未来を生きる子どもたちのために、
親は、子供以上に、学び続ける必要がある。
そして、そんな人のために、
私は未来食を発信していきたいと思っています。
子どもの食事に悩んでいる...という方は、レッスンに来てみてね!
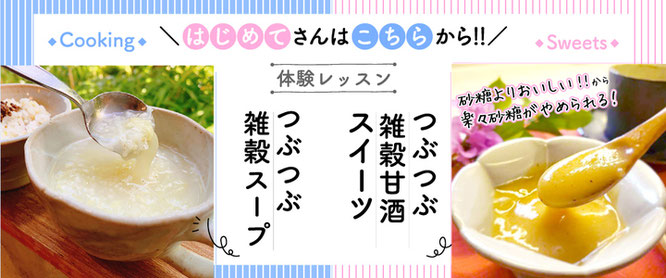
コメントをお書きください