
私たちの食卓に欠かせない「豆」。
その中でも、お赤飯やおはぎ、ぜんざいに使われる「小豆(あずき)」は、
特別な存在感を放っています。
漢字の「小豆」と、読みの「アズキ」って、
全然合わないような気がしませんか?
私は、小豆は日本原産なのでは、とずっと思ってました。
最近、あるニュースが私の中の確信を裏付けてくれました。
こんにちは!髙杉多希です。
訪問してくれてありがとうございます。
雑穀と野菜で作る家庭料理教室 たきさんちを主宰したり、
畑で雑穀や野菜を育てたりして、
Instagramで情報発信をしたりしています。
「たきちゃん」「たきさん」と名前で呼んでください♪
最近、あるニュースが目に飛び込んできました。
それは、「アズキは日本発祥だった」という科学的な研究結果。
2025年6月に報道されたこのニュースでは、
ゲノム解析により、小豆の起源が日本にあること
が明らかになったというのです。
🌱【参考】「アズキは日本発祥だった」農研機構と台湾大の共同研究(農研機構)
中国南部を原産とする説が長年有力とされてきましたが、
最新の解析によると、
現在栽培されているアズキの葉緑体DNA(母方から受け継がれる遺伝子)は
すべて日本固有の野生種「ヤブツルアズキ」と一致しているそうです。

※写真ACより。maki猫さんの写真。
原種であるヤブツルアズキでは黒味をおびている種皮の色が、
突然変異によって、赤くなったと考えられるそう。
ヤブツルアズキの種皮は固く、水を全く通さないのに対し、
赤い小豆は容易に吸水。
色が赤いことで美味しそうに見えたでしょうし、
水を良く吸うことは調理のしやすさ、食べやすさにつながります。
また、畑に蒔いた時に発芽しやすくもなります。
なので、
「なんだ、この赤いの!」
「すごく煮えやすい!」
「これ、おいしいじゃーん!」
「赤いのだけ集めて種を蒔こう!」
と、栽培と選抜を繰り返すうちに、
変異型の赤いアズキばかりになった
と考えられます。
そして、
赤いアズキの頻度は約1.3万年前から増加が始まり、
現在には赤いアズキが大半を占めるに至った。
ということです。
実は、私はこの研究結果を聞いたとき、「やっぱり!」と思いました。
といっても、ずっと勝手に日本原産だと思ってたので、
「え?中国原産ということになってたの?」という感じです(笑)。
というのも、名前が「アズキ」だから。
え?それだけ?と思うかもしれませんが、
名前ってすごく大切です。
科学と一緒で、日本語を突き詰めていくと、
どうしても由来が出て来ない段階が出てくる。
それが、原日本語だと私は思っています。
漢字で書くと「小豆」ですが、音読みなら「ショウズ」になるはず。
それでも私たちは「アズキ」と呼び続けてきました。
つまり、「名前」が先にあって、「漢字」が後から当てられたということ。
このパターン、実は他にもあります。
「さくら」→ 桜(音読み:オウ)
「すし」→ 寿司(音読み:ジュシ)
「はし」→ 橋(音読み:キョウ)
これらは、日本で生活の中から生まれた言葉に、
後から中国の漢字文化が融合してできた形です。
そして、アズキもまさにその一例。
日本語でしか説明できないもの。
昔から変わらず呼ばれている名前。
そこにこそ、文化と食の深い繋がりがあります。
「名前が残っている」ことが、
私たちの祖先の知恵や暮らしの証なのかもしれません。
そしてそれが、今回の科学的発見によって裏付けられたこと。
とても誇らしく、感動しています。
日本の言葉を大切にしていきたいから。
ちなみに、小豆は、
小豆にしかない色素=抗酸化成分を持っています。
2019年に発表された「カテキノピラノシアニジン」。
小豆餡の、薄紫色の成分です。
これが、「月に1~2回は小豆を食べよう」の根源かなと。
でも、砂糖を使ってしまうと、
その抗酸化力も無駄になってしまいます。
小豆の良さを活かすためにも、
砂糖を使わないつぶつぶ料理を多くの方に実践してほしいです。
これからも、料理を通して
そんな言葉のルーツや命の歴史を感じながら
伝えていきたいと思います。
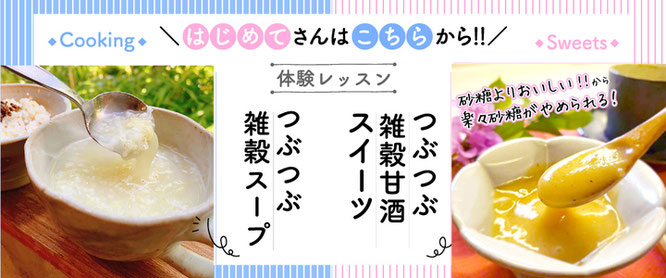
コメントをお書きください